どうも、ほにゃらら sp.です。
今回ご紹介するのは青メダカ。
青……というよりは、青みがかったグレーの体色を示すことからそう呼ばれるメダカです。
しかし!多種多様な青系の改良メダカは、この青メダカからはじまりました。
改良メダカとしてのみならず、ビオトープなどでも人気のメダカです。
青メダカとは

| 基本情報 | |
|---|---|
| 飼育しやすさ | ★★★★★ とても容易 |
| 入手しやすさ | ★★★★★ よく見かける |
| 維持しやすさ | ★★★★★ とても簡単 |
| 最大体長 | 3~4cm程度 |
| 適正水温 | 5~28℃ |
| 作出年 | 2004年 |
| 表現系の構成要素 | 青体色 |
青メダカは青系メダカのすべての原型とも言える品種です。
お世辞にも青とは呼べるかは微妙なグレー系の体色をしていますが、この発色をメダカにおいては最も基本的な「青」と表現します。
メダカの色素細胞は黒、黄、白、虹の4色あり、このうち黄色の色素細胞だけが欠乏したものが「青体色」と称されます。
この発色をかつては「シルバーブルー」と呼ぶこともありましたが、近年ではあまり使われなくなりました。
数々の青い色彩を持つ改良品種は、青メダカなしに世に出ることはなかったものと思われます。
改良メダカとしては基本中の基本という位置付けにあるため、青メダカそのものを系統維持していくといった楽しみ方は、近年ではあまりされないでしょう。
どちらかといえば、睡蓮鉢やビオトープで親しまれることの多い品種でもあります。

飼育のコツ
青メダカを上手に飼育するためには、次のポイントを意識すると良いでしょう。
観賞スタイル
上見、横見、どちらでも観賞が楽しめます。
グレー一色のシンプルな配色で、とても安価に入手できます。
このため、気軽にメダカを飼ってみたい!
という方にもおすすめです。

容器
エサ

白メダカ、黒メダカとの比較
青メダカはその名前ほど青々しい体色をしているわけではありません。
飼育環境によって体色が変わることもあります。
特に長い時間をかけた輸送の到着後は高確率で色が抜けており、白メダカに間違えられることもあります。
水槽で飼育している場合はグレーが強く見えることもあり、黒メダカに間違えられることもあります。
青メダカは青いメダカというより、「黄色みが無いメダカ」という表現がより正しいです。
白メダカに比べると黒みが無く、黒メダカに比べると黄色みがありません。
それが、青メダカの特徴なので覚えておきましょう。
バリエーション
青メダカの派生系として知られる人気品種をいくつか紹介します。
幹之(みゆき)

青ヒカリメダカ
青ダルマメダカ

青体色のダルマメダカです。
ダルマメダカの中でも基本的な表現の一つです。
色分けされて販売される基本体色のダルマメダカは年々流通が少なくなっていますが、ダルマメダカミックスとして販売される個体の中にそれらしい個体が一定数見られます。
青メダカ まとめ

青メダカ。
4色あるメダカの基本色の一つで、青系品種の最も基本形となるメダカです。
青というよりはグレーに近い発色ですが、メダカにおいて単純に「青」というとこの発色を指します。
基本的に青体色以外の余計な表現を持たないため、他の品種に青体色を導入したいときは交配させてみても良いかもしれません。
また涼し気な色合いから、ビオトープで泳がせるメダカとしても人気の高い品種です。

メダカ関連記事
メダカの世界
▼改良メダカの基本情報はこちら
改良メダカ個別解説
▼改良メダカ各品種ごとの詳しい解説はこちら



















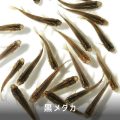





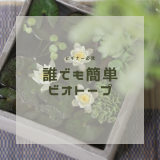
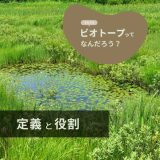


コメント