こんにちは、メダカ担当のスズキです(魚ではありません、人間です)。
世の中のメダカブームに乗ってメダカを飼い始めた人も多いのではないでしょうか。
「メダカの教室」は、そんなビギナー向けのなるほどシリーズです。
今回の授業は、屋内飼育のメダカをあえて冬眠させないという冬対策について。
やっぱりヒーターは必要?エサやり、水換えは?……心配なことはここで解決しましょう。
屋内飼育でもメダカは冬眠することがある
水温の低下とともにメダカの活動量は落ちていきます。水温が15℃あたりになると動きも鈍く、エサを食べる量も減るのが明らかにわかるでしょう。これはメダカが冬眠の準備に入っているためで、水温が10℃以下になるといよいよ冬眠状態になります。このように、冬眠の条件は水温であることから屋内飼育でも冬眠が起こり得るのです。
冬眠に入るとメダカはほとんど動かず、エサも食べません。少し心配になりますが、冬眠することで春まで体力を温存するために寿命を延ばせる、丈夫に育つといったメリットがあります。

無理にメダカを冬眠させない
寒い玄関など、水温が10℃以下になる環境ではメダカは冬眠状態に入ってしまいます。冬眠している間、メダカはほとんどエサを食べません(活動している様子が見られたら水を汚さない程度に与えても可)。水もほとんど汚れないため、水換えもいらず足し水程度で大丈夫です。

ただし、体が小さかったり、冬眠に向けて十分に栄養を蓄えていなかったりする場合、冬を越せずに死んでしまう可能性が高くなります。めやすとして、体長15mmあると冬眠が可能、20mmあると安心です。
また、冬から春にかけての水温変化についていけないメダカも出てきます。心配であれば無理に冬眠させずにヒーターで加温してあげましょう。冬を越すにはそれだけ体力が必要なのです。
リビングでは水温差に注意
メダカの水槽をリビングに置いている場合、暖房でポカポカ暖かいならヒーターは不要に思えるかもしれません。でも、就寝中や外出中はどうでしょうか。地域や住宅の構造にもよりますが、暖房を消すと冷え込むようであれば要注意。暖房のオン・オフの温度差が水温に影響を及ぼす可能性は大です。メダカは低水温に強くても水温変化が大きいと対応しきれず、体調をくずす原因になりかねません。
このような環境では、ヒーターを使うと水槽の水温が一定に保たれるので安心です。
水温計があると、ヒーターがきちんと稼動しているか確認できます。
ヒーターを使うメリット
ヒーターを使うことで水温が保たれると、寒い冬でもメダカは元気な姿を見せてくれます。ヒーターと照明をうまく使えば産卵を狙うことも可能です。安全に冬を越せるか心配ならヒーターを使うと良いでしょう。エサやりも水換えも普段通りに行います(水換えの際は水温差に注意)。
また、ヒーターを使うことで水槽に導入できる水草のバリエーションが広がる、熱帯魚との混泳を楽しめるといったメリットも見逃せません。
メダカと混泳できる熱帯魚はコチラから
メダカ飼育におけるヒーターの選び方
観賞魚用ヒーターは大まかにいうと、固定された温度に保温するもの、好みの水温に調節できるものがあります。温度が高いほど消費電力も多くなり、電気代がかかります。
普段通りに飼育できれば十分なら18℃保温でも良いでしょう。繁殖を狙うなら23℃に保温できるものがおすすめです。加温が必要な水草、熱帯魚を導入するなら、生育条件に合った水温に調節できる温度可変式が適しています。
オートヒーターなら
水温の維持が簡単

温度可変式なら水草・熱帯魚にベストな設定が可能

ヒーターには多くの種類がありますが、飼育目的から選ぶと比較的迷いません。また、水槽サイズに適していることも大切です。
ヒーターを使わず飼育する場合
冬眠状態になるほどの寒さでもなく、水温差も起こりにくい。そんな環境においては、ヒーターを使わずに飼育して構いません。ただ、水温が低下しているのであればメダカの消化活動も低下します。消化の良いエサを食べ切れる分だけ与えましょう。
まとめ
今回は、屋内飼育のメダカをあえて冬眠させないという冬対策についてお届けしました。
ヒーターを使うことで安全に冬を越しやすくなります。
それでは次の授業をお楽しみに!


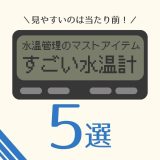









コメント