どうも、ほにゃらら sp.です。
今回ご紹介するのはナマズ。
日本全国各地に広く生息する淡水魚です。
古くから食用としても利用され、さまざまな伝承や文献にも登場するなど、日本人に古くから親しまれている魚です。
大きな口とどこかとぼけた表情が愛らしく、観賞魚としても人気の高い魚です。
観賞魚という視点では、大型肉食魚という括りに入るでしょう。
ナマズは日本産なので低水温にも強く、ヒーター不要で楽しめる大型肉食魚という見方もできます。
身近で入手しやすい魚なので、おたまじゃくしサイズの小型個体から育てることもよくあります。
最終的には80cm近くと、迫力のビッグサイズに成長します!
このため、飼育する場合はいずれ90cm以上の水槽を検討するなど、将来を見越した飼育計画を立ててから臨みましょう。
ナマズとは

| 生物学的情報 | |
|---|---|
| 名前 | ナマズ |
| 学名 | Silurus asotus |
| 別名 | ニホンナマズ、マナマズ、ヘコキ |
| 分類 | ナマズ目ナマズ科 |
| 食性 | 肉食 |
| 分布 | 日本(沖縄除く) 中国東部、朝鮮半島、台湾、アムール川、シベリア東部 |
| 飼育要件 | |
|---|---|
| 飼育しやすさ | ★★★☆☆ ふつう |
| 入手しやすさ | ★★★★☆ 入手しやすい |
| 混泳しやすさ | ★★☆☆☆ 混泳不向き |
| 最大体長 | 80cm |
| 適正水温 | 5~25℃ |
| pH | 生存可能:6.0~9.5 適正範囲:6.5~9.0 |
| 備考 | 近所で採れるかも? スレ傷に弱いので注意 |
全国各地に広く生息するナマズの代表種です。古くから食用として利用され、さまざまな伝承や文献から知られるとおり、日本人に親しまれてきた淡水魚の一つです。
外観は扁平した頭部と大きな口、ヒゲをもち、小さな背ビレが特徴的な種です。
池、沼、河川中下流域に生息しており、比較的汚れた川にも生息できます。
飼育する場合も水の汚れには強めです。
水質の観点では、飼育しやすい魚といえるでしょう。
ナマズは基本的に夜行性です。
昼間は物陰に潜んでいますが、夜は感覚器として発達した口ヒゲを利用して餌を探しに出かけます。
自然下では小魚、エビなどの甲殻類、昆虫、カエルなどを捕食しています。
肉食性のため、エサは生餌が基本です。
慣れさせれば、人工飼料に餌付く個体もいます。
見た目通りの大きな口で、口に入るサイズの生き物はなんでも食べてしまいます。
このため、基本的に他種との混泳は難しいです。
混泳にはあまり向いていないため、単独飼育が理想的です。
ナマズは物陰に隠れる習性がありますので、塩ビパイプや流木等で隠れ家を用意しましょう。
隠れ家を用意しないと落ち着かず、ストレスがかかってしまう場合があります。
同種同士では基本的にケンカしますが、隠れ家を増やすとケンカせず複数匹の混泳が可能になる場合もあります。
将来的には80cm以上と大型になりますので、90cm以上の水槽での飼育を考えておきましょう。
なお、成長スピードは比較的ゆっくりで、給餌量次第ではある程度サイズの調節は可能です。
給餌量を調節すれば、すぐに大きくなるということはあまりありません。
サイズが小さいうちは、60cm水槽での飼育も可能です。
有用なアイテム
ナマズは飼育設備に関して要求は低めです。
水槽サイズは90cm水槽以上が望ましいです。
フィルターに関しては、水の汚れには強いので何を選んでも構いません。
よく食べるぶん排せつ量も多いので、性能の良いフィルターを採用しておくとメンテナンスの頻度が少なく済みます。
餌に関しては基本的に活き餌を与えます。
餌付きやすさに関しては個体差が大きいようです。
すぐに人工飼料に慣れてくれる個体もいる一方で、一切口にしない個体もいます。
最初は活き餌を与え、徐々に冷凍餌、その次に人工飼料へと切り替えていくと良いでしょう。
最初から冷凍餌を食べてくれる個体であれば、人工飼料に慣れてくれる可能性も高いです。
| 水槽 | フィルター | 底床 | 餌 |
|---|---|---|---|
| 90cm以上 ※小型個体は60cm~可 | 投げ込み、外掛け、上部、外部 | 大磯砂、砂利、砂 セラミック | イトメ、赤虫、アカヒレ、クリル、人工飼料 |
90cm以上が望ましいです。
小型個体のうちは、60cm水槽でも飼育可能です。
体長が20cmを超えたあたりから、水槽のサイズアップを検討しましょう。
ナマズは驚くと暴れたように泳ぐことがあります。
水槽にはフタと、大型個体の場合は重石を乗せてください。

80cmほどの最大サイズに近い個体は、水槽を割ってしまうほどのパワーを持ちます。
できるだけ静かな場所に水槽を設置しましょう。
本種は水質に関しては寛容で、あまり細かい要求をしてきません。
幼魚のうちは投げ込み式、外掛け式でも十分です。
成長してくると排せつ量が増えるので、必要に応じて上部式や外部式などろ過能力の高いフィルターを採用すると良いでしょう。
▼フィッシュレットの併用も有効です。

ソイルと溶岩石砂以外であれば、何でも使えます。
本種は主に底床が砂礫の河川に棲んでいるのでソイルは不向きです。
体表を傷つけやすい溶岩石砂もナマズには向いていません。
大型個体は砂を巻き上げる点、また体表のスレを防止するべく角の無い底砂が理想的です。
ガーネットサンドは両方の条件を満たすため、おすすめです。
人工飼料も食べますが、最初のうちはなかなか餌付かないかもしれません。
小型個体ほど人工飼料に餌付きやすく、大型個体になるにつれて餌付きにくくなる傾向があります。
できるだけ小さいサイズから飼育を開始したほうが、餌付けには成功しやすくなります。
まずは生きたメダカやエビなどを与えると、高確率で食べてくれます。
幼魚のうちは冷凍赤虫を与えると良いでしょう。
慣れてくると、クリルも食べるようになります。
まずは活き餌からクリルへ切り替えるのを目指すと良いでしょう。
その後、クリルから人工飼料に切り替えると、比較的人工飼料に餌付きやすいです。

メダカは定番
成魚サイズであれば小型魚はエサとして有効です。
ナマズが小型のうちは、メダカではやや大きいこともあります。
アカヒレを与えると食べやすいでしょう。


活きたエビも有効です。
個体によっては大好物で、数十匹をぺろりと平らげてしまう個体もいます。
スジエビが食べられないサイズの個体の場合は、より小ぶりなミナミヌマエビなどを与えると食べてくれます。


人工飼料に餌付く個体は非常に飼育が容易です。
ただし、個体の性格による要素が強く、餌付いてくれるかどうかは個体次第です。
すぐに食べてくれる個体もいれば、一切受け付けない個体もいます。
個体によって好みがあるようですので、いろいろ試してみるのも良いかもしれません。
ナマズ用として販売されている、沈下性のものが良いでしょう。

人工飼料に餌付かせる前段階に有効です。
いきなり人工飼料は食べてくれない個体がほとんどです。
まずは活き餌からクリルに切り替え、クリルから人工飼料に切り替えるようにすると良いでしょう。

混泳について
原則的に単独飼育が無難です。
ナマズは他魚に対する攻撃性が高いため、基本的に混泳は不向きです。
特に昼間は寝ていて夜に行動を開始するため、昼間に混泳させると意外と混泳できているように見えることもあるため、注意が必要です。
夜にトラブルが発生し、朝見ると片方がいなくなっているなんてことも……。
▼こちらも参考
シェルターについて
ナマズは物陰に隠れることを強く好みます。
体をすっぽり覆える程度のサイズのある、シェルターなどの隠れ家が必要です。
元々物陰に潜む習性があるので、隠れ家がないと落ち着きません。
隠れ家を複数個用意しておくと、個体によってはケンカせずに混泳が成立する場合もあります。
ただし、これは個体の性格次第となる部分が大きいので、基本的にシェルターを入れたとしても混泳は難しいと考えておいたほうが良いでしょう。


近所で採集できるかも
ナマズは観賞魚としての流通はあまり多くありません。
しかし、全国各地の河川や用水路などに広く分布しており、普通に見られる魚です。
近所の川で探してみると、自力で採集できることもあるでしょう。
自力で採集するメリットは、生息地の環境を直に体験できることにあります。
飼育する場合、生息環境をできるだけ再現するように心がけると良いでしょう。
また、採集できるナマズは10cmにも満たない小型個体であることも多いです。
5cm以下のおたまじゃくしサイズであることもあるでしょう。
幼魚と成魚では口ヒゲの数が異なり、幼魚では6本ですが成魚になると4本になります。
網で狙うと小型個体が多いですが、釣りで狙うと大型個体が狙えます。
大型個体は体力があり水質的には飼育しやすい反面、エサに関しては餌付けしにくい傾向がある点に留意しておきましょう。
ナマズは場所選びが良いと、特に幼魚ではたくさん採れることもあります。
しかし性質上、水槽1つにつき飼育できる数は1匹までと考えたほうが良いです。
たくさん持ち帰っても飼いきれません。飼わない分は、リリースしましょう。
▼こちらも参考
ナマズは鱗がなく皮膚が弱いため、網で採集した際に傷つきやすいことが知られています。
その傷から、水カビ病を発症してしまうことも多いです。
採集で手に入れた個体は、トリートメントしてから飼育を開始することをおすすめします。
▼こちらも参考
病気について
ナマズは水質には比較的寛容ですが、皮膚が弱いため物理的なダメージに弱いです。
ダメージにより生じた傷口から、水カビ病や尾腐れ病(カラムナリス感染症)などを発症しやすい傾向があります。
特に採集してきた個体を新しく導入する場合、混泳魚がいる場合は注意が必要です。
水温の急激な変化は、白点病の発症を招きます。
発見が早ければ、体力がある魚なので塩水浴で治ることもあります。
ナマズ類は他の魚種に比べ、薬品類に弱い傾向があるといわれています。
投薬の際は、薬品の添付文書をよく読んでから行ってください。
▼こちらも参考
ナマズの寝相
人に慣れたナマズは、お腹を上にしてひっくり返って寝ることがあります。
水槽の環境に慣れ、外敵がおらず安心できる環境であることが分かると、このような行動を見せることがあるようです。
一見死んでしまっているかのように見えるので、慣れないうちは驚くかもしれません。
野生動物とは思えないほど無防備な姿で寝ることがありますが、慣れればこれもご愛嬌となるでしょう。
状態を崩していたり、病気を発症していたりするわけではないので治療の必要はありません。
ナマズ まとめ

ナマズ。
大きい口と扁平な頭を持ち、文化的にも古くからなじみ深い淡水魚です。
観賞魚としては「和製肉食大型魚」といった位置づけにあり、将来的には90cm以上の水槽での飼育を見込みましょう。
とはいえ、小さいサイズから育てたほうが餌付けしやすいこと、また給餌量によってある程度サイズの調節は可能です。
一定期間であれば、60cm水槽で飼育することもできます。
水質にほとんど注文もなく飼育は容易、ヒーターも不要です。
全国的に広く分布しているので、近所で採集できることもあるでしょう。
飼育をきっかけにして、ナマズへの理解をぜひ深めてみましょう!





























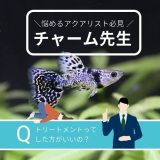





コメント