こんにちは、スズキです。
気温の上昇にともなって生き物の活動が始まると、小川や池、田んぼなどもにぎやかになってきます。
身近な生き物であるカエルも、春になると卵からかえってオタマジャクシとして水中で過ごします。
最近はカエル人気もあってカエルを飼育している人も多いようですが、採集しやすくカエルまでの変化を楽しめるオタマジャクシの飼育はいかがでしょうか。注意点だけを守れば飼育はとても簡単です。
日本に生息するカエルの代表種
日本には多くの種のカエルが生息しています。カエルの種類によって色や模様など姿がさまざまなように、オタマジャクシもやはり体型や色、大きさが異なります。オタマジャクシでカエルの種類がわかれば、あなたも立派なカエルマニア!
まずは比較的よく見かける種についてご紹介します。


オタマジャクシを採集する際に気を付けたいのが特定外来生物のカエルです。
名前をよく聞くウシガエルも実は特定外来生物で、ほぼ全国に分布が広がっています。
オタマジャクシや卵を含めてウシガエルを飼育する、生きたまま運ぶ、別の場所に放すことは外来生物法により禁止されています。持ち帰らないよう注意してください。
ウシガエルの特徴として、とにかく大きいことが挙げられます。
オタマジャクシの時点でも、尾を含めず胴体部分だけで4cmを超えていれば間違いなくウシガエルと判断して良いです。全長で15cmくらいに育つこともあります。
小型個体は見分けづらいのですが、野外で遭遇するサイズは8~10cm前後であることが多く、他の種類のオタマジャクシに比べても2~3倍くらい大きいので大抵は一目で区別することができるでしょう。
ちなみに、成体は鼓膜が目よりも大きい点が在来のカエルとは異なります。
緑~褐色のまだら模様をしていることが多いです。
その他、定着が認められたカエルにオオヒキガエル、シロアゴガエルがいます。
特定外来生物に指定されたものについては以下の項目について規制されます。
飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。
※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。輸入することが原則禁止されます。
※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。野外へ放つ、植える及びまくことが原則禁止されます。
※放出等をする許可を受けている者は、野外へ放つ、植える及びまくことができます。許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。
販売することも禁止されます。
許可を受けて飼養等する場合、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等できません。上記の規制のうち一部が適用除外される特定外来生物(通称:条件付特定外来生物)であるアカミミガメ、アメリカザリガニについては、一般家庭で飼育することは手続きなく可能です
環境省 日本の外来種対策
他にもカエルの中には天然記念物や絶滅危惧種に指定されている種もいます。
安易に採集しないよう気を付けましょう。
カエルの子はオタマジャクシ
カエルの繁殖能力は高く、種によって異なりますが、平均して500~1000個近くの卵を産みます。卵塊と呼ばれる卵から2~3日でふ化してオタマジャクシになります。
オタマジャクシは成熟するまでは水中ですごし、数回の変態をしてカエルへと成長していきます。
同じ両生類のウーパールーパーはまた違った成熟を行う種です。
下記の記事で詳しくご紹介しています。ぜひこちらもお読みください。
オタマジャクシの飼育方法・飼育用品
基本的に、オタマジャクシの飼育に最低限必要な用品は3つ。
「飼育容器」「水草」「カルキ抜き」があれば飼育を始めることができます。
今回は日本のどこでも見かけるアマガエルを基本とした飼育方法や設備をご紹介します。
飼育容器
オタマジャクシの体長は1cm程度と小さく、3匹程度なら中サイズのプラケースで飼育可能です。
※卵から飼育の際は大きな容器が必要になります。
終生飼育を考えているのであれば、高さのある30ハイの水槽や、管理のしやすさを考えると「GEX エキゾテラ グラステラリウム 」などもおすすめです。
ヒーター
春から夏にかけて生活を行うので、あまりにも低い水温での飼育は避けたほうが良いでしょう。
最適な水温は23~25℃程度で、サーモスタット付きヒーターであればしっかりと水温管理が可能です。30℃以上になる夏場ではファンなどによる調整も必要になります。
※オタマジャクシの動きは緩慢のため、ヒーターでやけどしてしまうことがあります。
ヒーターを設置する場合は、やけど防止にヒーターカバーなどが必須です。

カルキ抜き・中和剤
水道水での飼育は生き物にとって有害です。必ずカルキ抜きをしてから飼育水としてください。
水草
上記3つのアイテムに加えてぜひ導入してほしいのが水草です。
オタマジャクシは常に泳いでいるわけではありません。むしろ、じっと動かず休んでいることが多いです。葉の硬い浮き草か、マツモやアナカリスなどの水草を入れてあげると休憩場所や隠れ家のほか、エサにもなります。ストレス軽減のためにも入れてあげると良いでしょう。
水草を入れるのに底床が必要な場合は、砂利など自然の環境に近いものを使うと良いです。
オタマジャクシのエサ
オタマジャクシは草食性が強い雑食です。一般的にいわれているエサは、葉物野菜(ほうれん草はゆでる)、カツオブシ、ニボシなどを与えます。
草食性のエサを与えるだけでは成長不良になるので、動物性のエサもバランス良く与えるようにしましょう。
おすすめのエサ
Josh’s Frogs ダートフロッグ
動物性、植物性のタンパク質をバランスよく配合したオタマジャクシ専用フードです。
多くの種類のオタマジャクシに対応しています。
専用のフードでなくても、熱帯魚やエビ用のエサも食べます。
エサを与えた時の注意として、食べ残しがあれば取り出すようにしましょう。そのままにしておくと油膜やエサの腐敗で水が汚れてしまいます。
オタマジャクシ飼育の注意点
飼育にあたっては、次の点に気を付けましょう。
水位を深すぎないようにする
上下の動きが苦手なオタマジャクシにとって、深い水位での飼育は体力を減らすことになります。オタマジャクシが変態し、上陸する際にも浅瀬や陸地がないとおぼれてしまいます。
水位はオタマジャクシの体長の2倍程度をめやすにしてください。
上陸用の足場は必須!
ストレスを避ける
飼育容器の収容力を超えた匹数での過密飼育や、頻繁に水質の変化を与えるような水換えは避けましょう。過密飼育はお互いをかじってしまう原因になります。
他の生き物との混泳はやめよう
一緒に捕まえてきた魚やザリガニ、イモリと一緒に飼いたいと思う人もいるかもしれませんが、オタマジャクシは単独での飼育が基本。なぜなら、オタマジャクシは動きが遅く、攻撃されたり捕食されたりすることが多いからです。おいしくないのか?積極的に食べない魚もいますが、尾ビレだけかじられてしまうこともあり、混泳はさけたほうが良いでしょう。
素手で触らない
オタマジャクシにとって人間の体温は高く、素手で触るとやけどの原因になります。
アンモニア中毒に注意!
カエルをはじめとした両生類は、全身の皮膚でも代謝を行うのでアンモニア中毒になりやすいです。
対策として、エアレーションや硝化バクテリア剤の使用をおすすめします。それでも水槽のセット後にアンモニアが増える時期が危険になることも。特に水量の少ない容器での飼育では、水質悪化に注意する必要があります。
フィルター+エアレーションを使わない場合は、毎日水換えをしてあげると良いでしょう。
「アンモニアの量が増え過ぎる前に水を換える」のがポイントです。
おすすめの硝化バクテリア
エアレーションも兼ねた
投げ込み式フィルター
まとめ
オタマジャクシは丈夫で飼育は容易です。水辺なら都市部でも見かけることができるでしょう。
よくコケを食べてくれるため、意外と水槽をピカピカに維持しやすいものです。
基本的な飼育方法を押さえていれば、カエルに変態させることも難しくありません。
しかし、カエルになって以降の飼育方法は種類によってかなり変わるうえ、飼育も難しくなります。
覚悟を持って終生飼育に努めてください。採集場所であっても自然に戻してはいけません。
カエルの飼育で特に大変なこと
●口に入るサイズの生餌を常に用意しなければならない
→とりわけ上陸したてのカエルは小さな生餌を食べられるか確認が必要。
→大食漢なので常に食べられるようにする必要がある。
●成体は過密飼育が難しい
→成体になるとお互いある程度の距離を取るようになるので、その分広いケージが必要。
→皮膚から出す毒で自家中毒になりやすい。
→病気が発生すると一気にまん延する。
たくさんのオタマジャクシがカエルになった分だけ飼育はものすごく大変になります。
脱走にも注意が必要なため、飼育は数匹に留めておくのがベストです。
オタマジャクシを飼育するにあたり、必要な心構えをまとめると以下の通りです。
①カエルになっても終生飼育します。
②不意の脱走に注意します。
③たとえ採集した場所でも自然に戻してはいけません。
心構えができていれば、自由研究の教材としてもオタマジャクシ飼育は良いでしょう。
ぜひ水棲から陸棲への変態を間近で観察してみてください。

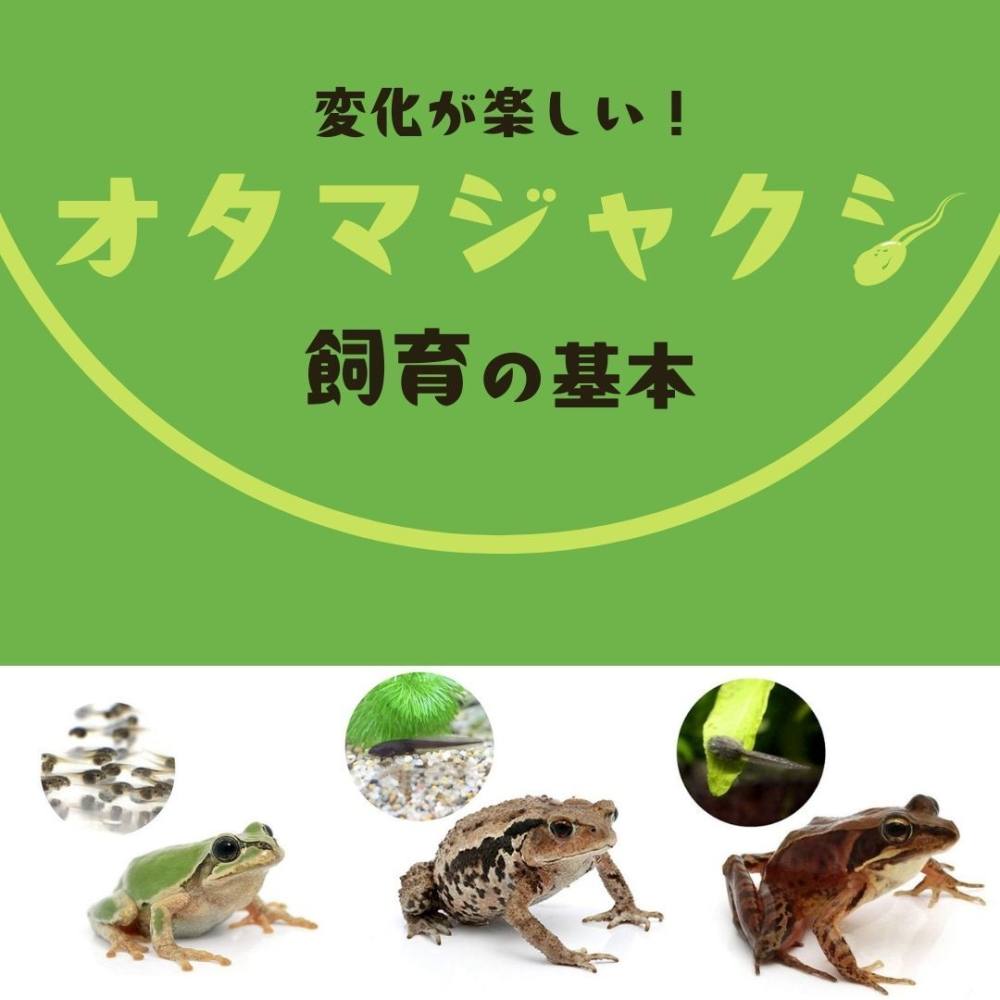






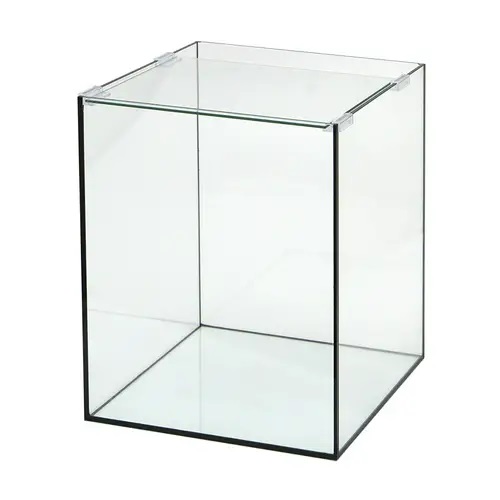















コメント